
この記事では、海外ドキュメンタリー『How to Live Forever(永遠に生きる方法)』を基に、多くの人が一度は夢見る不老不死の科学のリアルな最前線について解説します。
この記事を読めば、下記3つのことがわかります。
- 「健康寿命」派から「不老不死」派まで、老化に挑む3つのグループの思想と実践
- NMN、幹細胞治療、遺伝子治療…噂の若返り技術の科学的根拠と、そこに潜むワナ
- 億万長者ブライアン・ジョンソンは何者か?彼の過激な挑戦が問いかけるもの
▼ 情報元紹介
- 監督: サイモン・ケイド(Simon Cade)
- あらすじ: 世界各地の長寿者や科学者、医療従事者、有名人らへのインタビューを通じて、「長生き」とは何か、その価値や悩み、死への向き合い方を多角的に探るドキュメンタリー。監督自身が「永遠に生きることの意味」や「老いの現実」を追い求め、人生を豊かに過ごすためのヒントや哲学的な問いを投げかける。
- 出典元: How to Live Forever
※マーク・ウェクスラー(Mark Wexler)監督の同名映画とは異なる作品です。
※この記事は、ドキュメンタリーの紹介であり、医学的アドバイスではありません。健康に関する判断は必ず医師にご相談ください。
「若返り」に大金払う人って、結局「死ぬのが怖い」って認めてるだけじゃないの?
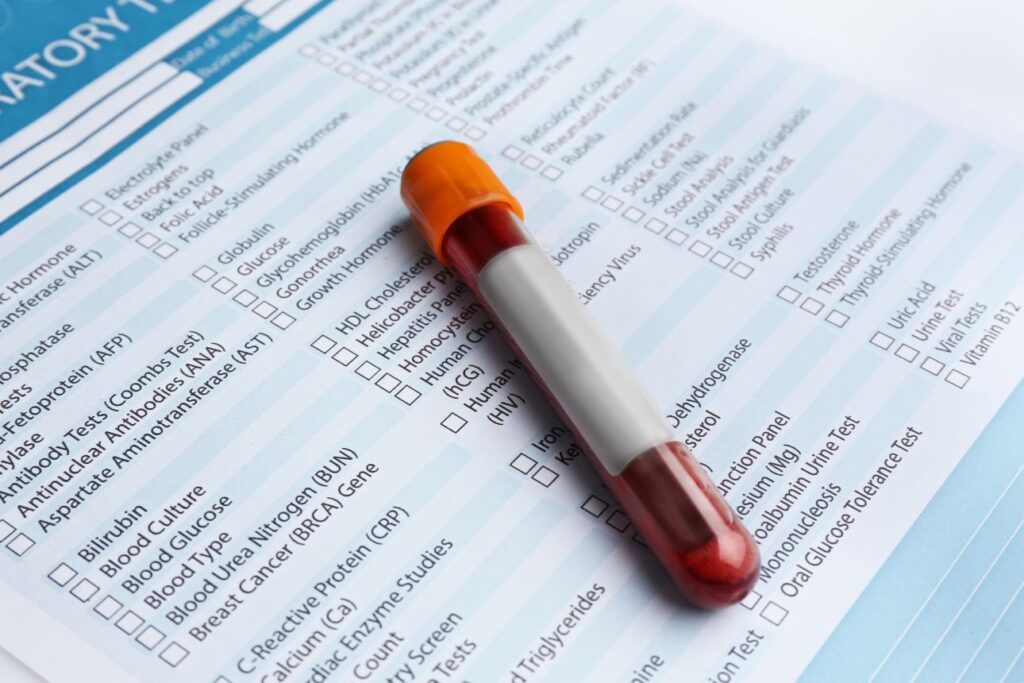
また歳をとり、飲む薬の数が、年々増えていく。そんな現実にため息をつく毎日。
世の中では「不老不死」だの「若返り」だの、景気の良い話が飛び交っています。年間数億円かけて自分の体を実験台にする億万長者のニュースを見て、正直こう思いませんか?「そんなにお金があっても、結局は死ぬのが怖いだけなんだな」と。
彼らのやっていることは、まるで高級ブランド品で不安を武装するかのように、最先端科学で「死への恐怖」を覆い隠そうとしているだけに見える。その必死さが、逆に痛々しい。そして、少しだけ、自分と同じ匂いを感じてしまう…。そんな、皮肉めいた共感を抱いているのは、きっと私だけではないはずです。
でも、その「永遠の命」の探求が、私たちの“長生きの恐怖”の正体を映し出しているとしたら?

分かります。私もかつては、怪しげな健康法に手を出しては裏切られ、高価なサプリメントに無駄金を払い、結局何も変わらない現実に絶望してきましたから。だからこそ、断言できるのです。
今回ご紹介するドキュメンタリー『How to Live Forever』は、遠い未来の話ではありません。私たちが今、目を背けている「老い」と「死」への恐怖、そのものなのです。
この映画が本当に問いかけているのは、「どうすれば永遠に生きられるか」という技術的な問題ではありません。むしろ、「死という終わりがあるからこそ、私たちはどう生きるべきか」という、私たち自身の根源的な問題。これは、もう他人事ではない。あなたの、そして私の物語なのです。
科学か、詐欺か。不老不死に挑む3つの思想と、その現在地

この映画には、大きく分けて3つのタイプの「挑戦者」たちが登場します。彼らの主張を知ることで、不老不死の科学のリアルな現在地が見えてきます。
アンドリュー・ヒューバーマン博士
まず登場するのが、彼に代表される、科学的根拠を重視する専門家たちです。「不老不死」のような非現実的な目標ではなく、運動、食事、睡眠といったライフスタイルの改善によって、病気や障害のない期間、すなわち「健康寿命」を最大化することを目指します。彼らのアプローチは最も現実的で、私たちが今日からでも取り入れられるヒントに満ちています。
経歴: スタンフォード大学医学部教授の神経科学者です。脳と行動を結ぶ神経回路やウェルビーイングに関する研究を推進し、自身の理論をもとに「脳と心を再設計する12の習慣」を提唱しています。YouTubeや各種ポッドキャストで一般向けに科学知識や科学的な自己改善法を発信し、幅広い世代に支持されています。
デイビッド・シンクレア博士
次に、より野心的なグループです。彼らは、NMNなどのサプリメントや最先端のバイオテクノロジーによって、生物学的な寿命そのものを180歳、あるいはそれ以上に延長できると信じています。しかし、その研究の多くはマウス実験の段階であり、その効果と安全性を巡っては、ビジネスとしての経済的な思惑も絡み、常に論争の的となっています。
経歴: ハーバード大学医学部教授であり、老化のメカニズムや若返り研究で世界的に著名な生物学者です。エピジェネティクスやサーチュイン遺伝子の研究、長寿分野の先駆的な成果で知られ、著書『LIFESPAN』では「老化は治療できる病」と主張しました。学術論文や企業設立も多数手掛け、科学と社会をつなぐメッセンジャーとして国際的な影響力を持っています。
ブライアン・ジョンソン
この物語の主役ともいえる、過激な実践者たちです。彼らは「死は克服可能である」という信念のもと、年間数億円を投じて自身の肉体を改造し、人体冷凍保存や、規制の及ばない海外での遺伝子治療といった、倫理の境界線をも踏み越える挑戦を続けます。彼らの姿は、私たちに「そこまでして生きたいか?」という根源的な問いを突きつけます。
経歴: PayPalマフィアの一員として巨万の富を得たIT起業家。うつ病と自殺念慮に苦しんだ過去を持ち、その経験から「死の運命に抗う」ことを人生の目的に定める。自身の体を徹底的にデータ化し、老化の逆転を目指す「プロジェクト・ブループリント」を主宰。息子の血漿を自身に輸血するなど、過激なパフォーマンスで世界的な注目と批判を集めている。
結論、私たちが明日からできる「最高の長生き戦略」とは?

このドキュメンタリーを見て、私たちが学ぶべきなのは、高価なサプリや過激なバイオハッキングではありません。むしろ、彼らの極端な挑戦が浮き彫りにした、もっとシンプルで大切なことです。
取材を進める中で、制作者はある事実に気づきます。思想は違えど、長寿を真剣に考える専門家たちが、口をそろえて同じことを言うのです。
それは、最高の長寿戦略とは、「最新の科学」に頼ること以上に、「人とのつながり」「生きがい」、そして「死を意識すること」にある、という真実です。
ブライアン・ジョンソン氏の孤独な挑戦は、私たちに問いかけます。「何のために、永遠に生きたいのか?」と。友人や家族との温かい時間、社会と関わることで得られる目的意識。そういったものを犠牲にしてまで手に入れる「長さ」だけの人生に、果たして意味はあるのでしょうか。
結局のところ、私たちが今日からできる最高の「老化防止」とは、特別なことではありません。健康的な食事や運動を心がけ、友人や家族と笑い合い、そして「自分はいつか死ぬ」という当たり前の事実を受け入れること。その覚悟こそが、皮肉にも、私たちに残された時間を最も豊かに、そして輝かせるのです。
みんなの生声
関連Q&A

Q. 不老不死を追求する科学的方法には何があるか
A:不老不死の科学的アプローチには、細胞の老化を抑える「テロメア制御」や、老化細胞の除去技術(セノリティクス)、iPS細胞による若返り研究、遺伝子治療、脳や意識をAIへ移す「意識のアップロード」などがあります。再生医療やエピゲノム制御も注目され、老化防止と延命のための研究が世界中で進行中です。
Q. 長寿の秘訣として紹介される食事や生活習慣は何か
A:長寿のためには栄養バランスのよい適量の食事を規則正しく摂り、たんぱく質やビタミン、食物繊維を意識。加えて適度な運動・十分な睡眠・ストレス管理も重要です。和食などの多様な食品を楽しみながら、飽食や低栄養を防ぐことがポイントとされています。
Q. ドキュメンタリーで語られる哲学的な死生観の違いは何か
A:ドキュメンタリーでは「死は終わりか、通過点か」「長生きは幸せか」など、多様な死生観が描かれます。古代~現代の哲学者による「死の無害説」や、「生きる意味は有限性に由来する」といった立場、“死”を恐れる感情の捉え方や宗教的・文化的な価値観の違いが浮き彫りになります。
まとめ
あらためて、今日の話の要点をおさらいします。
- 世界の最先端では、ライフスタイル改善から過激な遺伝子治療まで、様々なレベルで「老化への挑戦」が加速している。
- しかし、その多くは科学的根拠が乏しく、ビジネス的な思惑や倫理的な問題を孕んでいるのが実情である。
- 究極の長寿戦略はハイテクではなく、「人とのつながり」や「生きがい」、そして「死を意識すること」にある。
それにしても、私たち凡人にはとても真似のできない、壮絶な生き様です。でもね、それでいいんです。彼らのような人が、人間の可能性の限界を空の果てまでグーッと押し広げてくれるから、私たちは一歩立ち止まることができる。そして自分なりのペースで、誰かと手を取り合いながら、自分の「終わり」と向き合う準備をすればいいのです。
▼ では、100年時代をどう生き切るか──その実践のヒントを次の記事で探してみませんか。



