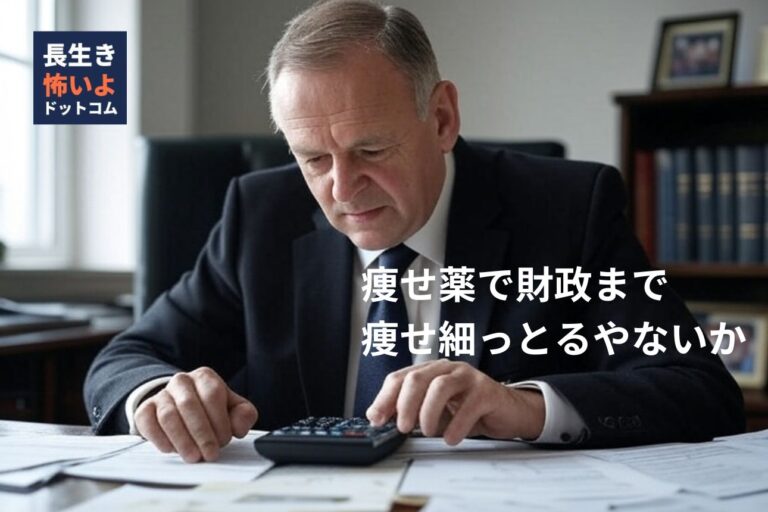この記事では、米国の資産管理学の権威、マイケル・フィンケ教授のインタビューを基に、多くの人が陥りがちな老後の資産運用の落とし穴と、それを避けて資産寿命を延ばすための科学的なアプローチについて解説します。
この記事を読めば、下記3つのことがわかります。
- 「年利12%で8%取り崩す」といった楽観論が、なぜ危険なのかという数学的な理由
- 退職直後の市場暴落(シークエンス・オブ・リターン・リスク)から資産を守る具体的な方法
- 個人で抱えきれない「長生きリスク」を、保険などの仕組みで賢く乗りこなす考え方
▼ 情報元紹介
- 話し手: マイケル・フィンケ(Michael Finke)教授
- 経歴: アメリカンカレッジ・オブ・ファイナンシャル・サービス教授で、フランク・M・イングル経済的安全性講座を担当。リタイアメント資金計画や高齢者資産管理、老後幸福度の研究で世界的に知られています。著名な学術論文や金融機関との協働研究も多数。米国の金融プランニング分野で高く評価され、講演やメディアでも活躍しています。
- 出典元: Savvly Retirement Roundtable Ep. 10: Conversation with Michael Finke
退職金で買った投資信託の評価額、毎日見ては一喜一憂…。

退職金、まとまったお金が手に入ったはいいものの、どう扱っていいか分からず、とりあえず銀行に勧められた投資信託、買ってみましたよね。
で、スマホのアプリを開いては、今日の基準価額がプラスかマイナスかで、心臓がキュッとなる。プラスの日は「よしよし」と少し贅沢な惣菜を買い、マイナスの日は「やっぱり普通預金が一番だったか…」と、どんよりした気分で一日を過ごす。
定年して時間ができたはずなのに、なんだか前より心が休まらない。こんな精神状態で、あと20年も30年も資産管理なんて、正直できる気がしない。でも、年金だけでは暮らせないし…。この、誰にも言えない地味なストレス、あなただけじゃありません。
なぜ、良かれと思った資産運用が、あなたを不幸にするのか?

私も、何度も失敗してきました。有名なインフルエンサーが「これからはこの株だ!」と言えば飛びつき、経済誌が「まだ間に合う新NISA!」と特集すれば、よく分からないまま積み立て額を増やしてみる。その結果、どうなったか。
市場が良い時は調子に乗って生活レベルを上げ、暴落が来ればパニックになって狼狽売り。気づけば、汗水たらして貯めたはずの資産が、手数料と損失で見るも無残な姿に…。もう、あんな思いは二度としたくないし、誰にもさせたくない。
なぜ、私たちの老後 資産運用は失敗するのか。それは、私たちが「ルール」を知らないからです。この記事は、過去の私のように、出口戦略のない航海に出ようとしているあなたを救うための、本気で書いた手紙です。
専門家が断言する、老後資産運用の「やってはいけない」鉄則とは?

ここからは、資産管理学の権威、マイケル・フィンケ教授が語る、私たちが陥りがちな「失敗のワナ」とその科学的な解説です。耳が痛いかもしれませんが、これを知っているか知らないかで、あなたの老後が天国と地獄に分かれます。
「年利12%で8%取り崩し」は、数学的に破綻しているという事実
巷には「高成長の株に投資して、高い利回りで取り崩せばOK」という楽観論が溢れています。しかし、これは致命的な欠陥を無視した暴論です。
- シークエンス・オブ・リターン・リスク: 株式市場は、毎年必ずプラスのリターンを約束するものではありません。特に、退職直後の1〜2年に大きな下落に見舞われると、資産全体が少ない状態から取り崩しを始めることになり、回復不可能なダメージを負います。これが、退職金運用で失敗する最も典型的なパターンです。
- 算術平均と幾何平均のワナ: 「1年目に50%下落し、2年目に50%上昇」しても、資産は75%にしかなりません。市場の変動(ボラティリティ)が大きければ大きいほど、手元に残る実質的なリターンは、見た目の平均リターンより必ず低くなります。この数学的な現実を無視した計画は、必ず破綻します。
老後資産の生命線「4パーセントルール」の本当の意味
では、安全な取り崩し率は何パーセントなのか。多くの研究が示す一つの目安が、有名な「4%ルール」です。
これは、資産の4%を毎年取り崩していく方法ですが、これも万能ではありません。フィンケ教授が指摘するのは、このルールが機能する前提として、生活の基盤となる収入は、リスク資産とは切り離して確保すべきだという点です。
具体的には、家賃や光熱費、食費といった、絶対に削れない「固定費」の部分は、株式ではなく、「債券ラダー」のような、値動きが安定した資産で確保することが推奨されます。満期の異なる複数の国債などを組み合わせ、毎年必要な現金が安定的に手に入る仕組みをまずつくる。これが、市場の嵐からあなたの生活を守る防波堤になります。
結論、「長生きリスク」は個人で戦うな。

ここまで読んで、「やっぱり資産運用って難しい…」と感じたかもしれません。その通りです。そして、個人で管理するには限界があります。特に、私たちがコントロールできない最大のリスク、それが「長生きリスク」です。
「長生き」がリスクになる時代の、最も賢い備え方
想定より長生きしてしまい、資産が底をつく。これほど怖いことはありません。フィンケ教授は、この個人では抱えきれないリスクに対処する最も効率的な方法が、「リスクの共同化(プーリング)」、つまり保険や年金の仕組みを活用することだと断言します。
例えば、「100歳まで生きたら1000万円もらえる」という個人年金保険を考えてみてください。早くに亡くなった人が払い込んだ保険料が、長生きした人の原資となる。これは、大勢で「長生きリスク」を共同で負担し合う、非常に合理的な仕組みです。
一人で100歳までの生活費をすべて貯めようとすると、現役時代の生活を極端に切り詰める必要があります。しかし、保険の仕組みを使えば、より少ない掛け金で将来の安心を確保でき、「今」の生活をもっと楽しむことができるのです。
あなたの人生のゴールは、貯金残高の最大化ではない
多くの人が、「死ぬ時に一番お金が残っていること」を目標にしてしまいがちです。しかし、それでは本末転倒。お金は、人生を豊かにするための「道具」にすぎません。
老後の資産運用の本当のゴールは、「安心して、生きているうちに必要なだけお金を使い切ること」です。そのためには、リスクを正しく理解し、コントロールできないリスクは保険のような仕組みに任せる。この割り切りこそが、失敗しないための最大の秘訣なのです。
みんなの生声
関連Q&A

Q:なぜ多くの人は老後資金運用で失敗しやすいの?
A. 主な原因は2つあります。1つ目は、退職直後という最も資産を取り崩してはいけない時期に、市場の大きな下落に見舞われる「シークエンス・オブ・リターン・リスク」を軽視してしまうこと。2つ目は、感情的な判断です。市場が良い時は楽観的になりすぎてリスクを取りすぎ、悪い時は恐怖に駆られて底値で売ってしまう「狼狽売り」をしてしまう。この心理的なワナが、長期的な資産形成を台無しにする最大の原因と言えるでしょう。
Q:どの投資商品が老後資金運用に最もリスクを伴う?
A. 一概に「これ」とは言えませんが、一般的に「個別株」や「テーマ型投資信託」、そして近年話題の「暗号資産」などは、価格変動(ボラティリティ)が非常に大きいため、退職後の安定した資産形成には高いリスクを伴います。これらの商品は大きなリターンが期待できる反面、資産が半分以下になる可能性も十分にあります。生活の基盤となる資金を、このようなハイリスク商品に大きく賭けるのは、非常に危険な戦略と言わざるを得ません。
Q:失敗しないために老後資産運用で気をつけるポイントは何かある?
A. 最も重要なポイントは、「生活費」と「余裕資金」を明確に分けることです。絶対に譲れない最低限の生活費は、国債などの安全資産で確保する。その上で、余裕資金の一部を、全世界株式のインデックスファンドのような、長期的に成長が期待できるリスク資産に振り分ける。そして何より、一度決めたルールを感情で曲げず、市場の動きに一喜一憂しないこと。この「規律」こそが、失敗を避けるための最大の防御策になります。
まとめ
あらためて、今日の話の要点をおさらいします。
- 市場の変動を無視した楽観的な取り崩し計画(例:12%ルール)は、数学的に破綻する危険性が高い。
- 生活に不可欠な固定費は、株式などのリスク資産ではなく、債券などで作る安定した収入で賄うべきである。
- 個人で抱えきれない「長生きリスク」は、保険や年金などの仕組みで他者と共同化(プール)するのが最も合理的。
これは、専門家や富裕層などの特定の人だけの話ではありません。思い切って保険の資料を一冊めくるだけで、背中の重りが少し軽くなるはず。まずは一歩だけ未来の自分を安心させる準備を始めてみませんか?